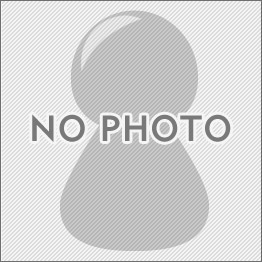shino さんの感想・評価
3.8
知の探究者たち
マッドハウス制作。
天文への情熱を捨てられずにいた神童ラファウ、
彼はフベルトという謎めいた学者に出会う。
彼が研究していたのは衝撃的なある仮説だった。
ラファウの信条は合理的に生きること、
合理的な選択をすればこの世は快適に過ごせる。
フベルトとの出会いが彼を変えていく。
こうして歴史に名を残さずとも、
情熱的に真理を追い求めた人たちがいる。
彼らはどんな苦難にも決して折れず、
世界を想像し知を探究したものたちである。
これは意志と継承の物語なのでしょう。
14話視聴追記。
世界はありのままで美しい。
{netabare}死刑宣告を受けたバデーニとオクジーは、
ある策に希望を託す、
それは後世に感動を伝えることである。
感動こそが学術的成果を復元させ、
地動説に新しい命を与える。{/netabare}
最終話視聴追記。
知性は揺らぎ迷うものである。
{netabare}知の探究者たちはそれぞれのやり方で、
真理と向き合い揺らいできた。
ついに物語は実在の歴史に繋がる。
コペルニクスは絵があっても良かった。
もう少し演出に余韻があればと思いますが、
人の叡智はこうして結ばれたのです。{/netabare}
とても興味深い物語で楽しめました。
知の探究者たちに、光あれ。